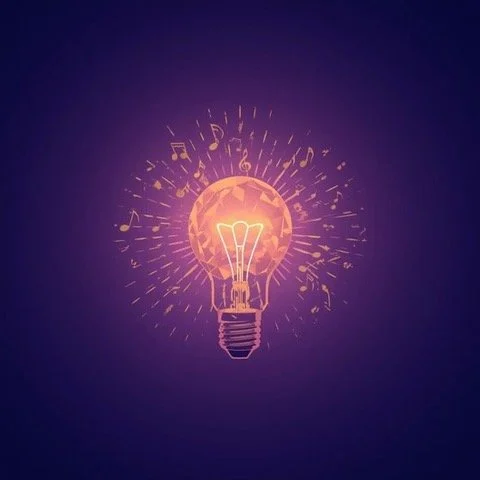ピアノの「ピッ!」シリーズ
ベートーヴェン ― 「被害者」か「勝者」か?
まず、コズモ・ブオーノによるベートーヴェンに関するエッセイをお読みください。そうすれば、この作曲家の人生が様々な試練に満ちていたことがわかるでしょう。彼は非常に才能に恵まれていました。しかしながら、天才として認められることはなく、一方で、父親から家族に富と安定をもたらす存在と期待されていました。彼はわずか17歳の時に母親を亡くしたため、ボンの実家に戻り、モーツァルトに師事するという計画を断念せざるを得なくなりました。モーツァルトとの共演は、彼の人生を永遠に変える可能性もあったのです。
作曲家としての並外れた才能以外でベートーヴェンについて多くの人が知っているのは、20代の頃に難聴になり、症状が悪化し自殺を考えるほどになったという事実です。この頃には、彼は音楽家としても作曲家としても確固たる名声を築いていました。科学者も歴史家も、彼の難聴は進行性の鉛中毒の結果だと考えています。当時、鉛はあらゆるものに使用されており、多くの人が食事をしていた皿にも鉛が使われていました。
ベートーヴェンは46歳までに完全に耳が聞こえなくなりました。驚くべきことに、彼自身の最高傑作のいくつかを彼が一度も聴くことがなかったという事実があります。交響曲第九番、ミサ・ソレムニス、ディアベリ変奏曲、最後の5つのピアノソナタ、そして晩年の弦楽四重奏曲はすべて、彼が聴くことのなかった傑作でした。彼は「難聴の犠牲者」だったと言う人もいるでしょう。一方で、他の作曲家であれば完全に諦めてしまうような病状を克服したという点を正当に指摘する人もいるでしょう。
彼がどのように作曲をしたのか…作曲はそれ自体が言語であり、ベートーヴェンはそれを十分に理解していました。そのため、彼は頭の中で音楽を「聞く」ことができました。彼の「内耳」の想像力は、音符、和音、和声に精通していたので、彼は頭の中ですべてを聞き、記憶からそれらの楽器を組み合わせたときの音を想像し、それに基づいて作曲することができたのです。
彼はまた、障害を克服するために、驚くような手段も講じました。例えば、ピアノの振動を感じるために顎をピアノに押し付け、さらに極端な方法として、ピアノの脚を外して床で振動を感じ取ることさえしたのです。
クラシック音楽家にとって、どんなに恵まれた環境下でも、仕事は非常に困難です。レパートリーを生き生きとさせるには、文字通り何年もの練習が必要です。これは、生涯にわたるキャリアの成功、あるいは何らかのキャリアを築くための探求を始める前のことです。
しかし、「犠牲者」と「勝者」を分ける、シンプルな要素が一つあります。
「勝者」は決して諦めません。
ベートーヴェンは、生涯を苦しめた困難に屈することなく、ピアニスト兼作曲家としての道を歩み続けました。死後200年近く経った今でも、彼は間違いなく最高の作曲家の一人とされています。もし彼が人生の困難に屈していたら、たとえ聴力を失う前であっても、素晴らしい音楽の遺産はなかったことでしょう。
現代の「勝者」の例として、ピアニストの辻井伸行を考えてみましょう。生まれつき目が見えないため、彼はすべてを耳で覚えなければなりません。それでも、2009年のヴァン・クライバーン・コンクールで金メダルに並び、2011年にはキーボード・ヴィルトゥオーゾ・シリーズの一環としてカーネギーホールで演奏しました。また、数多くのアルバムをリリースし、ウラディーミル・アシュケンジー、ケント・ナガノ、佐渡裕など、世界的に著名な指揮者たちと共演しています。
1824年5月7日、交響曲第九番の初演中、聴覚障害を持つベートーヴェンは鳴り響く拍手に気づいていませんでした。ソリストの一人、キャロライン・ウンガーが彼をそっと振り向かせ、聴衆の方に向かわせました。聴衆はベートーヴェンに熱烈なスタンディングオベーションを送りましたが、ベートーヴェンはそれを見ることができても、耳で聞くことはできませんでした。
今週の「ひらめきの瞬間」は何でしょうか?
それは、自分が「被害者」になるのは、そうすることを選んだ時だけであり、「勝者」になるということは、どんな障害にも乗り越える方法を見つけることです。「犠牲者」になるということは、人生が自分を支配することです。「勝者」になるということは、自分が人生をコントロールするということです。
勉強している作品の一部が難しいと言ってはいけません。簡単になるまで練習しましょう。曲が長すぎて暗譜できないと言ってはいけません。完全に暗譜で演奏できるようになるまで、小さな部分に分割しましょう。「勝者」であるベートーヴェンのように、自らの運命を支配し、自らの魂の指揮者になりましょう。